2023年4月より「NHK Eテレ」で、アニメ「青のオーケストラ」が放送開始となりました。
現在「マンガワン」と「裏サンデー」で連載中の、阿久井真さんによる漫画が原作です。
現在進行形で漫画を読んでいる方はもちろん、原作を知らない方でも楽しめる内容となっています。
私は原作を読んでおらず、予備知識はあまりない状態ですが。
アニメが放送されるということで、全話観るつもりでいます。
この記事では、アニメ「青のオーケストラ」で登場したクラシック曲を全話紹介していきます。
性質上、ネタバレとなる部分がありますので、ご注意いただければと思います。
所々、分からなかったり、見逃していたりする曲があるかもしれませんが、気づき次第、追記・修正していく予定です。
また、曲紹介でアップしている音源は全てフリー素材を使っています。
こちらのサイトから利用させていただきました。
>>「クラシック名曲サウンドライブラリー」
一部改変しているものもありますが、ご了承ください。
青のオーケストラの見逃し配信動画を見れるのはどこ?おススメのサービスをご紹介!
第1話で登場した曲一覧
第1話で登場した曲を、以下にまとめました。
「ヴァイオリン協奏曲 ホ短調」第3楽章/メンデルスゾーン
- 曲名:「ヴァイオリン協奏曲 ホ短調」第3楽章
- 作曲者:メンデルスゾーン
アニメが始まった直後に、回想シーンで青野一が演奏していた曲です。
メンデルスゾーンの「ヴァイオリン協奏曲 ホ短調」、いわゆるメンコンです。
第3楽章の終曲の部分が演奏されていました。
透き通るような音色で、聴き惚れました(^^♪
おそらく、設定としては、全楽章演奏したということだと思います。
ちなみに、ドラマ「リバーサルオーケストラ」でも、メンコンの第3楽章をアレンジした曲が毎回登場していました。
主人公の天才ヴァイオリニストの初音のテーマ曲という感じでした。
ただ、一般的になじみがあるのは、第1楽章かなと思います。
第1楽章の出だしの部分は、おそらく誰もが耳にしたことがあると思います。
いきなりサビを持ってくるという…
今では特に珍しいことではありませんが、当時は画期的なこと。
曲の冒頭でヴァイオリンのソロをたっぷり聴かせるようにしたのは、メンデルスゾーンが初めてと言われています。
また、メンデルスゾーンは、ニ短調のヴァイオリン協奏曲も作曲していたようですが、こちらはあまり知られていません。
多分、私は聴いたことがないと思います(汗)
一般的に、メンコンといえば、ホ短調の協奏曲になりますね。
オープニングテーマ/「Cantabile」
- 曲名:「Cantabile」
- 作詞:竹中雄大
- 作曲:竹中雄大/沖聡次郎
青野くんのメンコン演奏直後に、オープニングとなりました。
Novelbrightの曲です。
ありふれたこのフレーズも
~
~
気がするんだよ
のところの歌詞が、すごくいい!
著作権の関係で、歌詞を載せるとアウトになるので、これ以上は書けませんが…
でも、ほんと、素敵な曲でしたね(^^♪
「24の奇想曲」第24番/パガニーニ
- 曲名:「24の奇想曲(カプリース)」第24番
- 作曲者:パガニーニ
回想シーンで、青野くんの父親の青野龍仁がヴァイオリンで弾いていた曲。
青野くんが憧れの眼差しで、喜んでいました。
パガニーニの「24の奇想曲」で、最も有名な24番です。
パガニーニはヴァイオリンの演奏がうますぎたので、悪魔に魂を売り渡したのと引き換えに演奏技術を手に入れたと、まことしやかに噂されました。
大げさに聞こえますが、「24の奇想曲」を全部視聴すると、そのように信じられても仕方ないと思えるほど、強烈なインパクトがあります。
よく、こんな曲作ったなぁ…と。
青野くんのお父さんは、パガニーニが少しモデルになっているのかな?
原作を読んでいないので詳しいことは分からないのですが、風貌などちょっと似ているような気がします。
また、「24の奇想曲」の第24番は、後にリストやブラームス、ラフマニノフなど有名な作曲家がこぞって編曲し、モチーフにした曲を作ったことでも有名ですね。
このブログの色んな記事で述べていますが、ラフマニノフ大好きな私としては、「パガニーニの主題による狂詩曲」がぜひとも聴いていただきたいおススメの曲です。
ラフマニノフのパガニーニの主題による狂詩曲が使われた映画は?隠れた名作「ある日どこかで」を紹介します!
パッヘルベルのカノン
- 曲名:3つのヴァイオリンと通奏低音のためのカノンとジーグ ニ長調
- 作曲者:パッヘルベル
保健室で、秋音律子がヴァイオリンで練習していましたが。
何の曲か、よく分かりませんでした(汗)
パッヘルベルのカノン?
G線上のアリア?
音が延びるところが、エルガーのエニグマ変奏曲にも聞こえるのですが…
やっぱり、何度聴いても分かりませんでした。
ヴァイオリンに詳しくて実際に弾いてらっしゃる方なら、分かるのかもしれませんね。
第2話で明らかになるかもしれないので、待つことにします。
そして、第2話の内容から、どうやらパッヘルベルのカノンだったようです。
正式名称は「3つのヴァイオリンと通奏低音のためのカノンとジーグ ニ長調」ですが、一般的にはパッヘルベルのカノンの名称で知られていますね。
特に第1曲目のカノンは有名で、誰もが聴いたことがある曲でしょう。
逆に、2曲目のジーグはあまり聴く機会はないと思います。
上記で使わせていただいた音源も、前半のカノンのみで後半のジーグは収録されていませんでした。
ジーグがないので、パッヘルベルのカノンという愛称が広まったとも考えられます。
でも、ジーグも素敵な曲なので、ぜひ全曲通して聴くのをおススメします(^^♪
エンディングテーマ/「夕さりのカノン feat.『ユイカ』」
- 曲名:「夕さりのカノン feat.『ユイカ』」
- 作詞・作曲:粗品
エンディングテーマは、「夕さりのカノン feat.『ユイカ』」という曲で、曲名にあるとおり、パッヘルベルのカノンを基調としたメロディーでした。
所々で取り入れられているカノンのアレンジが絶妙で、聴き入ってしまいました。
エンディングテーマもいい曲ですね。
で、驚いたのが、作詞・作曲が粗品さんということ!
知らなかった~
ビックリしました…
粗品さん、すげえなぁ。
改めて、その多彩な才能に脱帽です。
第1話のまとめ・感想
まだ1話だけですが、これからの展開が楽しみで仕方ないという感じです。
早く続きが見たいです。
原作を読んでいないので、原作を見たいという誘惑にかられていますが、我慢してます(笑)
青野くんを演じている声優さんは千葉翔也さんで、個人的に「ようこそ実力至上主義の教室へ」の主人公・綾小路くんの印象が強いです。
無気力なところは青野くんと似ているかな。
秋音役の加隈亜衣さんは、やはり「鬼滅の刃」の真菰が有名ですかね。
最近見たアニメだと、「転生したら剣でした」のフランも、すごい印象に残っています。
どちらも、いわゆる萌えキャラ的な存在ですが。
秋音はまたちょっと違うタイプですね。
うまく演じ分けているのが、さすがだわ~と感心いたします。
あと、それぞれのキャラクターの演奏を担当している方々がすごい!
青野くんは東亮汰さんで、父親の青野龍仁はヒラリー・ハーンさん。
めっちゃ豪華なメンバーですね。
物語だけでなく、随所で演奏されるクラシック曲にも期待しています。
第2話で登場した曲一覧
第2話で登場した曲です。
ほぼ、第1話と同じでした。
「ヴァイオリン協奏曲 ホ短調」第3楽章/メンデルスゾーン
- 曲名:「ヴァイオリン協奏曲 ホ短調」第3楽章
- 作曲者:メンデルスゾーン
武田先生が、中1のときの青野くんのコンクールでのヴァイオリンの音が忘れられないと言ったとき。
BGMとして流れました。
生演奏した曲のようですが、BGMとして使うのは贅沢な選出ですね。
「24の奇想曲」第24番/パガニーニ
- 曲名:「24の奇想曲(カプリース)」第24番
- 作曲者:パガニーニ
青野くんが秋音律子に頼まれて、ヴァイオリンの弦を直しているとき。
秋音にヴァイオリンを弾いてほしい言われ、自宅にマスコミが押し寄せている回想シーンで流れました。
第1話でも登場した24の奇想曲の第24番ですね。
パッヘルベルのカノン
- 曲名:3つのヴァイオリンと通奏低音のためのカノンとジーグ ニ長調
- 作曲者:パッヘルベル
秋音律子が練習していた曲です。
パッヘルベルのカノンであることが判明しました。
1話目では分からなかったです。
微かにカノンの感じがしましたが、何やら別の曲が混じっているような気もしました。
2話目では、1話目よりうまくなっているような…
かなりカノンに近づいているような気がしました。
ただ、青野くんが鼻歌でカノンを口ずさんでいましたが、こちらの方がカノンとすぐに分かりました(笑)
そして、圧巻だったのが、ラストの青野くんの演奏シーン。
シチュエーションが素敵すぎる!
これは反則だわ~
しかも、カノンが流れたまま、エンディングロールを迎えるという、とても粋な演出(^^♪
いや~、感動して、ちょっと泣きそうになりました。
映画を観ているようでした。
第2話のまとめ・感想
話がちょっと重いなぁ~と感じましたが、それゆえに引き込まれますね。
青野くんの内面描写も、とても細かくて。
原作はまだ連載中ですよね?
なのに、第2話ですでに泣きそうになりました…
感動したなぁ。
あと、ヴァイオリンの演奏以外にもBGMがありましたが、クラシックかもしれません。
ちょっと分からないです(汗)
つい最近のドラマ「リバーサルオーケストラ」を見ていて、清塚信也さんによるクラシックのアレンジがたくさんあったので、青のオーケストラのBGMもアレンジ曲かもしれないと身構えています。
リバーサルオーケストラも、主人公が初音という女性で、小さいころに天才ヴァイオリニストとして名をはせたという点で似ていました。
青野くんはメンコンで、初音はチャイコン。
色々と対比すると、なかなか面白いです。
さて、次回から高校に舞台が移るようですね。
本格的にオーケストラが始動ということで、期待しています。
第3話で登場した曲一覧
第3話で登場した曲です。
といっても、クラシックは1曲だけでした。
いや、正確には1曲しか分からなかったと言うべきかも…
時おり流れるBGMが、何かのクラシックのような気もするのですが。
もし、正確なことが分かれば、追記いたします。
「軽騎兵」序曲/スッペ
- 曲名:「軽騎兵」序曲
- 作曲者:フランツ・フォン・スッペ
第3話のラストシーン、海幕高校の部活動紹介で、シンフォニックオーケストラ部が演奏していた曲。
スッペの「軽騎兵」序曲です。
「軽騎兵」序曲は、昔から色々なシチュエーションで聴く機会が多いですね。
今でも、ドラマやCMなどのBGMでよく使われます。
実際、日本テレビ系ドラマ「それってパクリじゃないですか?」の番組予告PR動画で使われていました。
「軽騎兵」はもともとスッペが手がけた喜歌劇、ライトオペラですが、現代では上演されることはありません。
というか、「軽騎兵」のあらすじが今では分かっておらず、記録も残っていないんです。
なので、上演するにも、上演できないというわけです。
「軽騎兵」序曲は、誰もがよく聴く馴染みのある曲ですが、なぜか喜歌劇の「軽騎兵」は内容が分かっていないという不思議な状態となっています。
また、スッペが「軽騎兵」を制作しようと思ったきっかけは、オッフェンバックの「天国と地獄(地獄のオルフェ)」を観て、触発されたからと言われています。
「天国と地獄」はとても有名な喜歌劇で、ご存じの方も多いでしょう。
特に序曲は、運動会の徒競走でよく使われる定番の曲です。
オペラの内容自体も現在よく知られており、グルックの「オルフェオとエウリディーチェ」をパロディ化したものとなっています。
全体の物語としては、ギリシア神話のオルフェウスとエウリュディケーのくだりをモチーフにしています。
第3話のまとめ・感想
「軽騎兵」序曲のオーケストラがすごかった~
生で聴いているようなものなので、さすがに圧倒されました。
間違いなく、3話の最高のシーンでしょう。
しかし、部員が164名もいるというのはビックリしました(笑)
あと、秋音が家にやってきてから、青野くんのお母さんがよく笑うようになったこと。
過去に辛い経験があったようですが、秋音とも気がねなく話せているようで、少し安心しました。
ちょっと大げさかもしれませんが、お母さん、幸せになってほしいです。
第4話で登場した曲一覧
第4話で登場した曲を紹介しています。
演奏シーンの曲は分かるのですが。
BGMで流れる曲が、相変わらず気になります。
クラシックのような気もするし、ジャズのような気もします。
詳しいことが分かれば、追記していきます。
「無伴奏チェロ組曲 第1番」前奏曲(プレリュード)/バッハ
- 曲名:「無伴奏チェロ組曲 第1番」前奏曲(プレリュード)
- 作曲者:バッハ
山田くんが楽器店で演奏していた曲です。
山田くんが、曲紹介していましたね。
無伴奏チェロ組曲は6番まであります。
そして、その1~6番全てが
- 前奏曲→アルマンド→クーラント→サラバンド→メヌエット→ジーグ
- 前奏曲→アルマンド→クーラント→サラバンド→メヌエット→ジーグ
- 前奏曲→アルマンド→クーラント→サラバンド→ブーレ→ジーグ
- 前奏曲→アルマンド→クーラント→サラバンド→ブーレ→ジーグ
- 前奏曲→アルマンド→クーラント→サラバンド→ガヴォット→ジーグ
- 前奏曲→アルマンド→クーラント→サラバンド→ガヴォット→ジーグ
という順に、規則正しく6曲で構成されています。
ただ、一般的になじみがあるのは、やはり1番でしょう。
無伴奏チェロ組曲のプレリュード(前奏曲)も、普通は1番のプレリュードを指します。
正直、私は6番まで全てをじっくり聴くことは、そんなに多くありません(汗)
それでも、1~6番まで全て優雅な響きで、ゆったりした気持ちになりますね。
また、今でこそ、バッハの無伴奏チェロ組曲は有名ですが。
バッハの死後は、ほとんどその存在は忘れられてしまいました。
バッハの自筆譜も現存していないようです。
しかし、今や伝説のチェリストとも言える、パブロ・カザルスが再発見し、その価値を広く世に知らしめたのは有名な話ですね。
パブロ・カザルスの存在がなければ、今の時代に、無伴奏チェロ組曲が当たり前のように演奏されることはなかったと考えられます。
「四季」より「春」第1楽章/ヴィヴァルディ
- 曲名:「四季」より「春」第1楽章
- 作曲者:アントニオ・ヴィヴァルディ
物語のラスト近く。
オーケストラ部の見学中に、青野くんが、佐伯直と一緒にヴァイオリンで弾くことになった曲。
佐伯くんがさわりだけ演奏しました。
「四季」は、言わずと知れた、ヴィヴァルディの代表曲。
特に「春」の第1楽章は、最も有名でしょう。
入学式のシーズンに、よく聴く機会が多いと思います。
もともとは「和声と創意への試み」というヴィヴァルディの協奏曲集に収められており、「四季」は最初の4曲のセットになります。
春・夏・秋・冬のそれぞれに3つの楽章があり、合計12楽章から成り立っています。
個人的な印象かもしれないですが、12楽章全てを聴くと、「四季」のそれぞれのメロディーが、日本の一般的な季節のイメージと違うような気がするんですよね。
特に「夏」は3楽章とも、不安をかき立てられるような曲調です(汗)
逆に、「冬」の第2楽章は、なぜか陽気…
やはり、ヴィヴァルディは17~18世紀のイタリアの人なので、今の日本とは風土も文化も違うし、季節のとらえ方も異なるのだと思います。
それでも、「春」の第1楽章の明るい雰囲気は、日本の一般的なイメージと共通していますね。
また、「四季」には、全ての楽章に「ソネット」と呼ばれる詩が付けられています。
ヴィヴァルディ自身が書いたものと思われますが、真偽のほどは分かっていません。
春の第1楽章のソネットは
で始まり、途中で嵐が来て、嵐が通りすぎると、小鳥たちは再び楽しそうに歌うというような意味になります。
第4話のまとめ・感想
う~、ここで終わるか~という感じでした。
ちょうど、いいところで次回へ続くとなりましたね。
青野くんと佐伯くんの直接対決?が気になります。
四季の「春」第1楽章もたっぷり聴けるのかな?
楽しみですね。
あと、バッハの「無伴奏チェロ組曲 第1番」前奏曲が、少しだけしか聴けませんでした。
できれば、もうちょっと聴きたかったな~というところです。
そして、アニメの中で、オーケストラについての知識を教えてくれるのがありがたいですね。
勉強になります。
でも、秋音ちゃんが、1stヴァイオリンやコンマスという用語も知らなかったのは、どうなんだ?
オーケストラ部に入るのであれば、それくらいの予備知識は普通ありますよね。
まあ、やっぱり、そういうキャラなのかな。
ツッコミどころが多くて、かわいいです(^^♪
オーケストラの解説をするために、あえてそういう設定にしたとも考えられますね。
第5話で登場した曲一覧
第5話で登場した曲です。
相変わらず、BGMで流れる曲はちょっと分からないです…
「四季」より「春」第1楽章/ヴィヴァルディ
- 曲名:「四季」より「春」第1楽章
- 作曲者:アントニオ・ヴィヴァルディ
前回から続くような形で、ヴィヴァルディの春の第1楽章です。
青野くんと佐伯くんが、バトルのようになって演奏した曲。
その後、小桜ハルも演奏しました。
そして、オーケストラ部の2~3年生が、1年生の前で披露しました。
どちらも、すごい迫力でしたね(^^♪
パッヘルベルのカノン
- 曲名:3つのヴァイオリンと通奏低音のためのカノンとジーグ ニ長調
- 作曲者:パッヘルベル
オーケストラ部の見学で、秋音律子が自ら立候補して演奏した曲。
秋音ちゃん、かなりうまくなってましたね(^^♪
回を追うごとに成長しているのが、よく分かります。
「軽騎兵」序曲/スッペ
- 曲名:「軽騎兵」序曲
- 作曲者:フランツ・フォン・スッペ
青野くんが、2~3年生の演奏を待ってる間、原田蒼を見て、回想シーンで流れました。
3話で、部活動紹介のときにオーケストラ部が演奏していた曲ですね。
BGMのような形で流れていたのが素敵でした。
第5話のまとめ・感想
やっぱり、ヴィヴァルディの四季の演奏がすごかったですね。
ソロバージョンとオーケストラバージョンの両方を聴かせてもらった感じです。
原田先輩がコンマスとなって率いたオーケストラの演奏は圧巻でしたね。
青野くんと佐伯くんの、ソロ対決の演奏もかなり聴きごたえがありました。
すごいインパクトがあったので、個人的にはこちらの方が印象に残ってしまったかも…
普段、オーケストラのそろった演奏に聴き慣れているからかもしれません。
第6話で登場した曲一覧
第6話で登場した曲です。
いつものように、時折BGMで流れる曲は気づいていない可能性があります…
「カルメン」より「前奏曲(闘牛士)」/ビゼー
- 曲名:「カルメン」より「前奏曲(闘牛士)」
- 作曲者:ビゼー
オーケストラ部が、定期演奏会に向けて練習していた曲です。
練習中、青野くんが合わせるのが難しいと言ってました。
その後、秋音が足を引っ張らないようにと、一人で練習していましたね。
ビゼーが制作したオペラ「カルメン」の「Les Toreadors(=闘牛士)」ですが、歌劇では、序盤の第1幕への前奏曲として演奏されます。
さあ、これから始まるぞ!という感じですね。
今でも様々な場面で、よく耳にすることがあると思います。
有名どころでは、「ビートたけしのTVタックル」のオープニングテーマかな。
それだけ馴染みのある曲ですが、オーケストラの場合、通常はオペラのカルメンの曲を再編成した「カルメン組曲」として演奏されます。
アニメでは定期演奏会で発表する曲のようなので、カルメン組曲が披露されるのでしょう。
で、ビゼーはカルメン上演後しばらくして急死したため、カルメン組曲は、ビゼー自身が編曲したものではありません。
そのため、現在では、一口にカルメン組曲といっても、オーケストラによって選曲や順序・構成も違ってきます。
これが結構ややっこしくて、管弦楽団によって様々なバージョンがあるので、混乱してしまうこともあると思います。
Les Toreadorsも「前奏曲」とか「序曲」というタイトルで披露されることもあるようです。
ただ、カルメン組曲では、Les Toreadors(闘牛士)は、最初に演奏されることが多いという印象です。
その他、組曲には「ハバネラ」や「アラゴネーズ」などもあり、これらもドラマやCMなどでよく耳にすることがあると思います。
アニメの定期演奏会でも、これらの曲が出てきそうですね。
また、オペラのカルメン自体もすごい迫力があるので、ぜひご覧になっていただければと思います。
カルメンが歌う「ハバネラ」や、エスカミーリョが歌う「闘牛士の歌」など、組曲とはまた違った魅力を感じられることでしょう。
「くるみ割り人形」より「小序曲」/チャイコフスキー
- 曲名:バレエ組曲「くるみ割り人形」より「小序曲」
- 作曲者:チャイコフスキー
6話の終わりの方で、オーケストラ部が練習していた曲です。
ご存じのとおり、チャイコフスキーの有名なバレエ作品「くるみ割り人形」。
その序曲となります。
先ほどのカルメンと同じように、オーケストラで演奏されるときは、組曲として再編成されたものが披露されるのが通常です。
組曲としてのくるみ割り人形は
- 小序曲
- 行進曲
- 金平糖の精の踊り
- ロシアの踊り
- アラビアの踊り
- 中国の踊り
- 葦笛の踊り
- 花のワルツ
という編成になります。
アニメで練習していた曲の小序曲は、バレエでも最初に登場する曲で、その流れで第1幕へと続きます。
くるみ割り人形の組曲はどれも有名ですが、特に「行進曲」と「花のワルツ」は、誰もが聴いたことのある曲でしょう。
でも、小序曲もとてもいい曲ですよ。
小気味の良いテンポで、聞いていると心が躍りますね。
あと、個人的に好きなのは、ロシアの踊りです。
迫力のあるメロディで、テンションが上がるので、気合を入れたいときなどに聴くことがあります。
まあ、この辺は、人それぞれ好みがあるでしょう。
また、最近色々な場面でやたらとよく聞くのが、金平糖の精の踊り。
ドラマやCMなどで、BGMとして使用されているのをよく見かけます。
さて、アニメ6話では小序曲のみ演奏されていましたが、定期演奏会では全曲演奏されるのか、期待しています。
ちなみに、バレエのくるみ割り人形の原作は、ホフマンの童話作品「くるみ割り人形とねずみの王さま」となります。
今では電子書籍でも読めたりします。
で、それをさらに、アレクサンドル・デュマが翻案したものが、チャイコフスキーのバレエ作品の直接の台本となっています。
アレクサンドル・デュマは、「ダルタニアン物語(三銃士)」や「モンテクリスト伯」の作者として有名ですね。
ちょっと話がそれますが、この2作品はガチで面白いので、機会があれば、ご一読することをおススメします。
第6話のまとめ・感想
カルメン組曲もくるみ割り人形も、ヴァイオリンのみの演奏でしたが。
これが興味深かったです。
普段オーケストラで聴くので、ヴァイオリンで音合わせをしている風景は、逆に新鮮でした。
意外にも、貴重なものを聴かせてもらったという印象です。
また、仮入部が終わり、定期演奏会に向けて本格的な練習をするとはいえ、入部したばかりの1年生がカルメンやくるみ割り人形を演奏するものなのかと、少しビックリしました。
定期演奏会でどこまでの曲を演奏するか分かりませんが、特にカルメン組曲だと難度の高い曲があるので。
この辺の事情はよく分かりませんが、やはり日本でも有数の高校のオーケストラ部なので、それだけレベルが高いものなのかなと思いました。
第7話で登場した曲一覧
第7話で登場した曲を、以下にまとめました。
「くるみ割り人形」より「小序曲」/チャイコフスキー
- 曲名:バレエ組曲「くるみ割り人形」より「小序曲」
- 作曲者:チャイコフスキー
7話の最初で、オーケストラ部が練習していた曲です。
青野くんと小桜ハルちゃんが隣になって練習していました。
「スケルツォ・タランテラ」/ヴィエニャフスキ
- 曲名:スケルツォ・タランテラ
- 作曲者:ヘンリク・ヴィエニャフスキ
青野くんと小桜ハルちゃんが、小学生のときのコンクールで一緒になり、青野くんが演奏した曲です。
ちょうど出だしの部分を演奏していました。
ヴィエニャフスキの「スケルツォ・タランテラ」ですが、フリー音源は見つかりませんでした…
ヴィエニャフスキはポーランドのヴァイオリニストで作曲家。
「華麗なるポロネーズ」や「2つのマズルカ」など数々のヴァイオリン曲を作曲し、ヴァイオリンのショパンと呼ばれることがあります。
アニメで登場したスケルツォ・タランテラは、ヴァイオリンとピアノの協奏曲で、特にヴァイオリンはかなりの技巧曲として知られています。
スケルツォはイタリア語で「冗談」という意味のとおり、もともとは軽快なテンポでユーモア感のある曲のことでした。
ただ、次第にその意味合いは薄れ、曲調は楽曲によって異なるようになりました。
スケルツォといえば、やはり、ショパンが楽曲の一分野として確立したとイメージが強いですね。
ショパンが作曲したスケルツォの4曲は、まさにピアノ曲のクラシックの王道という感じ。
また、「スケルツォ・タランテラ」のタランテラは、イタリアの港町タラントに由来するとか、毒蜘蛛のタランチュラに由来するとか、諸説アリです。
なぜタランチュラ?と疑問に感じますが、タランチュラに噛まれると毒に冒されるため、苦しんで踊り続けてしまうからという説によります。
さて、スケルツォ・タランテラは、かなりの技術が必要となるヴァイオリンの難曲です。
これを、小学生2年生の青野くんが弾くのか…
しかも、小桜ハルちゃんは、ブルッフでしょ。
お互い、レベルが高すぎる(汗)
と思っていたら…
クレジットに青野くんの吹き替え演奏は、江原望花子さんとありました。
存じ上げなかったのですが、プロとして活躍しているヴァイオリン奏者の方と思っていました。
ところが、たまたまYouTubeで検索をかけてみたところ、まさかまさか、現在小学生の女の子のようなんです。
そして、スケルツォ・タランテラを演奏している動画も、たまたま拝見しました。
音楽コンクールの全国大会の模様を撮影したもののようです。
ただ、ご本人なのかどうかは確証を得てません。
そのため、ここでは動画の掲載などは控えさせていただきます。
とはいえ、実際に、これだけの技術を持つ天才的な小学生がいらっしゃるものなんですね。
感服しました。
その後、江原望花子さんのお母さまから情報をいただき、ご本人であることが分かりました。
そして、お母さまの許可を得て、望花子さんが実際にスケルツォ・タランテラを演奏している動画を掲載させていただきました。
いや、ほんとすごいです。
何回聴いても、聴きほれてしまいます😆
改めて、感服しました。
「カルメン」より「前奏曲(闘牛士)」/ビゼー
- 曲名:「カルメン」より「前奏曲(闘牛士)」
- 作曲者:ビゼー
7話の後半で、オーケストラ部が練習していた曲です。
このときは、青野くんと佐伯くんが隣になって演奏しました。
第7話のまとめ・感想
物語の前半は、ほのぼのしていて、青春だなぁ~と思って見ていましたが。
後半に入ってから、またもや話が重すぎる…
ハルちゃん、気の毒すぎる…
自分を変えようと思っても、そう簡単にできるものではないですもんね。
ハルちゃんの小学2年生のコンクールの様子が描かれていたので、その後も親目線で見てしまいました。
見ていて泣きそうになることもありますが、音楽が心を癒してくれるのを期待しています。
第8話で登場した曲一覧
第8話で登場した曲をまとめました。
「カルメン」より「前奏曲(闘牛士)」/ビゼー
- 曲名:「カルメン」より「前奏曲(闘牛士)」
- 作曲者:ビゼー
6話・7話に続いて、オーケストラ部が練習していた曲です。
カルメンの練習のときは、青野くんと佐伯くんが隣同士になるようです。
佐伯くんが、小桜さん今日も部活休み?とつぶやいていましたね。
G線上のアリア/バッハ
- 曲名:G線上のアリア
- 作曲者:バッハ/ウィルヘルミ
8話終盤で、秋音のリクエストに応え、ハルが演奏した曲です。
G線上のアリアも、誰もがどこかで聞いたことがあるであろう、有名な曲ですね。
もともとは、バッハが作曲した「管弦楽曲第3番」の第2楽章「アリア」という曲ですが。
19世紀に活躍した、ドイツのヴァイオリニストてあるアウグスト・ヴェルヘルミが編曲し、G線上のアリアとして広く知られるようになりました。
では、なぜG線上のアリアという曲名になったのかというと?
ヴァイオリンのG線だけで弾けるからというのが、一般的な説です。
まあ、これは、とても有名な話ですね。
ヴァイオリンには4本の弦がありますが、G線は最低音の弦となります。
で、そのG線だけで、曲の最初から最後まで弾けちゃうということです。
ただ、なぜG線にしたのかは、よく分かっていません。
ヴェルヘルミがG線だけで弾けるのを発見した!と、よく言われていますが。
当時、ヴァイオリンのG線だけで演奏することが流行っていたとも言われています。
あるいは、G線はヴァイオリンの音の基準となる弦でもあるので、G線で弾くというのは自然なこととも考えられます。
いずれにせよ、1本の弦だけを使って演奏するというのが、聴衆を魅了するものであったのは間違いないものと思います。
また、バッハの原曲は様々な楽器で演奏される管弦楽曲でしたが、ヴェルヘルミが現在のようなヴァイオリンの曲へと編曲しました。
ヴェルヘルミがG線上のアリアとして復活させるまで、バッハの原曲は忘れ去られていたようです。
ちなみに、ドイツ語では、Gは「ゲー」と発音します。
そのため、G線上のアリアは「ゲーセンじょうのアリア」と読めたりします。
英語読みだと「ジーセン」ですが、ドイツ読みだと「ゲーセン」…
これも、クラシックあるあるとして、よく知られている小ネタです。
第8話のまとめ・感想
7話に続いて、重い話でした…
それにしても、登場人物の心理描写がエグいですね。
戦慄さえ覚えました。
作者の阿久井真さん、すごいなぁ。
ただただ感服するばかりです。
また、8話のタイトルでもあったG線上のアリアは、移弦せずにヴァイオリンの1つの弦だけで演奏するので、ハルと秋音の関係を象徴しているような気がします。
ハルが言っていたように、ヴァイオリンは早く次の弦に移動しようと焦りすぎても、うまくいかないですし。
友人関係も同じなのかなと。
それに、ハルが初めて秋音に披露した曲が、G線上のアリアですもんね。
と、まあ、あくまで勝手な解釈です😅
とにもかくにも、ラストのハルの演奏はめちゃめちゃ感動しました。
さすがに涙腺がやばかったです。
これからまだ困難はあるかもしれませんが、何とか一歩前進したようで、少し安心しました。
第9話で登場した曲一覧
第9話で登場した曲です。
「四季」より「春」第1楽章/ヴィヴァルディ
- 曲名:「四季」より「春」第1楽章
- 作曲者:アントニオ・ヴィヴァルディ
青野くんが、3年生がもうすぐオーケストラ部引退となる話を聞き、定期演奏会が終われば、もう先輩とは演奏できないのかとつぶやく場面。
回想シーンと共に、BGMのような形で流れました。
「交響曲第9番」第3楽章/ドヴォルザーク
- 曲名:「交響曲第9番(新世界より)」第3楽章
- 作曲者:ドヴォルザーク
定期演奏会に出演するメンバーのオーディションとして、ドヴォルザークの交響曲第9番の第3楽章を中心としてテストすることとなり。
2年生が1年生の前で披露しました。
9話ラスト近くでも、青野くんと佐伯くんが教室で練習していましたね。
ドヴォルザークの交響曲第9番は、ドヴォルザークがアメリカ滞在中に作曲した作品で、「新世界より」の愛称で広く知られています。
よく言われているのは、新世界はアメリカのことを指しているということですね。
ドヴォルザークがこの曲を作ったのは、アメリカの黒人やインディアンの民族音楽が、自身の故郷のボヘミアの音楽に似ていることに触発されたからと、一般的に考えられています。
で、アメリカという新世界より故郷を想って作曲されたので、「新世界より」という呼び名になったいうわけです。
ですが、ドヴォルザークが作曲した経緯を考えると、「新世界=アメリカ合衆国」というよりは、「新世界=アメリカの民族音楽」という方が、より正確かもしれません。
また、交響曲第9番は機関車の音のイメージが取り込まれていることで有名です。
とにかく、ドヴォルザークは機関車が大好きな人!
今で言うなら、生粋の鉄道オタク(笑)
これもよく知られている話ですね。
なので、「新世界=SL」という考えもあるくらいです。
さて、アニメでは、交響曲第9番の第3楽章が演奏されました。
よりによって、第3楽章…
ドヴォルザークの交響曲第9番といえば、やはり第2楽章と第4楽章が有名だと思います。
第2楽章は「遠き山に日は落ちて~」の愛唱歌になってますし、第4楽章は至るところでBGMとして使われているのを聴きますしね。
そこをあえて外して、第3楽章を演奏するのは、青野くんの言うとおり、いやらしいところを突いてきます(笑)
ですが、実際に第3楽章は、ヴァイオリンの難しいパート。
青野くんの解説のとおり、3拍子なので、ヴァイオリンだと拍が取りづらいんです。
と、まあ、私はプロではないので、あまり詳しいことは語れないですが(汗)
ともかくも、ヴァイオリン奏者の方のみならず、第3楽章はリズムがとりにくい、慣れるまで時間がかかるというのは、ちょこちょこ聞く話です。
第3楽章は、第2楽章の叙情的な余韻を残しつつ、軽快なリズムになりますしね。
そして、ダイナミックな第4楽章へと続いていく。
ドヴォルザークの交響曲第9番を全楽章聴くと分かりますが、やはり緻密に構成されています。
当たり前のことですけど…
個人的に、第3楽章がなければ、第4楽章の壮大さも完全には成立しないという印象を持っています。
第1楽章と第2楽章の旋律が形を変えて奏でられ、高揚感を高めながら、第4楽章にバトンタッチしているという感じでしょうか。
あまり馴染みがないかもしれませんが、第3楽章も聴き惚れる曲なので、じっくりと聴いていただければと思います。
第9話のまとめ・感想
青野くんと佐伯くんが、教室で練習するシーンが見ごたえがありました。
交響曲を2つのヴァイオリンの音色だけで聴くというのは、めったにないことなので、とても貴重。
しかも、すごい迫力でしたし。
当然のごとく、聴き入りました。
こういう面白い体験ができるのが、青のオーケストラというアニメの醍醐味ですね。
また、羽鳥先輩のキャラがよかったなぁ~
ああいうマイペースな性格は、見ていて気持ちがいいです。
第10話で登場した曲一覧
第10話で登場した曲です。
演奏されたのは、過去に登場したカルメンとドボ9第3楽章の2曲だけのようです。
が、演習風景で、順序が前後して何度か登場したので、ちょっとややこしいかもしれません。
「カルメン」より「前奏曲(闘牛士)」/ビゼー
- 曲名:「カルメン」より「前奏曲(闘牛士)」
- 作曲者:ビゼー
アニメが始まってすぐに、音楽室で部員が練習しているシーン。
秋音がおなかすいたとつぶやいたあたりまで、少し流れてました。
その後、2ndヴァイオリンの午後の合奏練習で部員が弾いていました。
さらに、立花さんが、完全下校の時間まで練習し、朝練でも弾いていた曲。
そして、ラスト近くで、2ndヴァイオリンの合奏練習で部員たちが弾いた曲となります。
「交響曲第9番」第3楽章/ドヴォルザーク
- 曲名:「交響曲第9番(新世界より)」第3楽章
- 作曲者:ドヴォルザーク
秋音が、練習中のハルに声をかけたときに、ハルと青野くんと佐伯くんが練習していた曲。
その後、秋音も1人で何度か練習していました。
第10話のまとめ・感想
今回は、いい話でしたなぁ~
物語後半は、ほんわかしながら見てました。
立花さん、周りのことよく把握していて、めっちゃ、しっかり者!
言ってること的を射てますよね。
特にオーケストラの場合は、音を合わせないといけないですから。
青野くんでも、飛びぬけて演奏うまいですが、音を合わすのに苦戦してましたし。
秋音に関しては、なおさらでしょう。
でも、秋音もそれに気づいて、ちゃんと立花さんに歩み寄ったので、1段階クリアというところですかね。
ただ、立花さんも、もう少し初心者さんに優しく接してもいいんじゃないのかなとは思います。
今後、2人は仲良くなっていくのかな?
あと、時々、作中のキャラが2頭身のような感じになるのも、面白くてかわいいです。
そうすることで、メリハリがついて、さらに見やすくなっているのだと思います。
そして、アニメで流れるBGMについてですが。
ドビュッシーの月の光や、坂本龍一さんの戦場のメリークリスマスをアレンジしたような曲が流れた気がしました。
ただ、自分がよく知っている曲に引っ張られている可能性があります。
なので、あまり説得力なしということで…
自分が知らなかったり、思い出せない曲がありそうで、もどかしさが絶えません(汗)
第11話で登場した曲一覧
第11話で登場した曲です。
「くるみ割り人形」より「小序曲」/チャイコフスキー
- 曲名:バレエ組曲「くるみ割り人形」より「小序曲」
- 作曲者:チャイコフスキー
青野くんと佐伯くんが補習しているときに、青野くんが音楽室から聞こえてくる曲に気付いたシーン。
…だと思うのですが、こちらはちょっと自信ありません
ヴァイオリンだけの演奏になると、私のような素人には、途端に分かりにくくなってしまいます(汗)
その後、青野くんと佐伯くんが補習が終わって廊下を走っているときと、音楽室へ入ろうとしているときに、鮎川先生指導のもと、部員が練習していた曲です。
2人が練習に遅れたこともあり、演奏されていたのは、曲の後半部分のようです。
「交響曲第9番」第3楽章/ドヴォルザーク
- 曲名:「交響曲第9番(新世界より)」第3楽章
- 作曲者:ドヴォルザーク
オーディションの曲とあって、何度も登場しました。
- 青野くんの家で、青野くんと秋音が一緒に練習した曲
- 佐伯くんが自宅で練習していた曲
- 羽鳥先輩が学校で練習していた曲
- 小桜ハルが自分の部屋で練習していた曲
となります。
特に、青野くんと秋音が音を合わせて演奏するシーンが、素晴らしかったですね。
1stヴァイオリンと2ndヴァイオリンの共演を、たっぷりと聴かせていただきました(^^♪
また、秋音がドヤ顔で、ドヴォルザークの「交響曲第9番」の説明を披露していましたね(笑)
第9話で、ドボ9第3楽章の解説をしておりますが、かなり内容がかぶっちゃいました。
ですが、もちろん、秋音の解説はそのとおりで一般的な解釈となっています。
第11話のまとめ・感想
サブタイトルのとおり、決戦前夜という感じでしたね。
見ている方も、ちょっと緊張しちゃいます。
個人的に特に印象に残ったのは、佐伯くんのおばあ様かな。
とてもいいキャラしてました。
さて、次回はついにオーディションですね。
ドボ9「新世界より」の第3楽章が中心になりそうですが。
それ以外の楽章も登場しないかなと期待しています。
第12話で登場した曲一覧
第12話で登場した曲です。
「交響曲第9番」第3楽章/ドヴォルザーク
- 曲名:「交響曲第9番(新世界より)」第3楽章
- 作曲者:ドヴォルザーク
オーディションの曲ということで、鮎川先生の前で部員たちが披露した曲ですね。
廊下にも響き渡っていました。
なかでも、圧巻だったのは、やはり青野くんの演奏。
いや~、ガチですごかった~
そして、
「すいません、先輩。正直、俺、1ミリも緊張してないです」
というセリフ!
かっけ~!!
ちょっと鳥肌ものでした。
「交響曲第9番」第1楽章/ドヴォルザーク
- 曲名:「交響曲第9番(新世界より)」第1楽章
- 作曲者:ドヴォルザーク
青野くんが夢の中で弾いていた曲。
佐伯くんに、「早く譜面めくってくれな~い?」と促されていました。
ドボ9の第1楽章だと思うのですが、ちょっと自信ありません(汗)
第3楽章の最後かもしれません。
ドヴォルザークの交響曲第9番では、いわゆる第1主題と呼ばれるパートがあります。
青野くんが夢の中で弾いていたのは、まさにその部分。
上記の音源だと、ちょうど2分くらい経ったところから流れます。
で、この第1主題は、まず第1楽章で奏でられ、その後、各楽章で登場します。
と、まあ、私は専門的なことはよく分からず、あまり深くは語れないですが💦
第3楽章では、ちょうど最後に登場し、そのまま曲が締めくくられます。
青野くんが夢の中で弾いていたのも、第3楽章の終結部のような気もします。
でも、第3楽章の拍子ではないような気がするんですよね。
私には、第1楽章のリズムのように感じました。
ただ、物語の流れ的には、第3楽章がふさわしいでしょう。
オーディションの曲が第3楽章ですし。
う~ん、どうなんだろ…
何ともあやふやな説明になって申し訳ありませんが(汗)
ぜひ第1楽章もお聴きいただければと思います。
個人的に、第1楽章の始めの部分や第1主題も、機関車のイメージが取り入れられているような印象をもっています。
第12話のまとめ・感想
武田先生と鮎川先生の関係が気になって、思わずウィキペディアを見てしまい…
わき見をして、思いっきり、登場人物のネタバレをくらってしまいました(汗)
ちょっとショックです…
先の展開が気になって仕方がない状態となっております😅
それはさておき。
第12話の最大の名シーンは、何といっても青野くんの演奏ですね。
第3楽章のヴァイオリンのソロを聴いているようなもんでしょ。
青野くんのヴァイオリン担当・東亮汰さんの演奏をたっぷりと聴かせてもらいました。
素晴らしい演奏を聴かせてもらい、ほんとありがとうございます!ですね(^^♪
これから、佐伯くんとの直接対決もあるようですし、楽しみは尽きません。
第13話で登場した曲一覧
第13話で登場した曲をまとめました。
相変わらず、「月の光」のような曲がBGMで流れていましたが、これはよく分からないです(汗)
「華麗なるポロネーズ」第1番/ヴィエニャフスキ
- 曲名:「華麗なるポロネーズ」第1番
- 作曲者:ヘンリク・ヴィエニャフスキ
青野くんが、人生初めてのコンサートで弾いていた曲ですが。
よく分かりませんでした…
エア・ヴァリエ?
あるいは、ザイツの曲とか?
という感じがしたのですが。
う~ん。
ヴァイオリンに詳しい方に聞かないと、分からないですね💦
13話のクレジットにあったように、青野くんのコンサートでの演奏は、江原望花子さんが担当しています。
また、望花子さんのお母さまから情報をいただき、演奏していた曲は、ヴィエニャフスキの「華麗なるポロネーズ」第1番であることが分かりました。
アニメでは、幼少期の青野くんが緊張してうまく弾くことができませんでしたね。
そして、望花子さんのお母さまに、少しだけお話を伺うことができたのですが。
あえて緊張している感じを出すように、努めたそうです。
お母さまの言葉を借りると、「ヴィブラートをかけ忘れた風の左手と、固くなってしまった右手で」表現してみたとのことです。
でも、しっかりと原曲をとどめながら、緊張している感じもうまく伝わってますよね。
とても興味深いお話、ありがとうございました(^^♪
さて、ここから、ヴィエニャフスキの「華麗なるポロネーズ」第1番の簡単な説明となります。
ポロネーズはフランス語で「ポーランド風」という意味で、ポーランドが起源のダンスのことですね。
ポロネーズは「タンタタタッタッタッ~♪」という感じのリズムを刻みますが、それを曲にしたというところです。
また、ポロネーズといえば、これまたショパンの曲が有名ですね。
特に英雄ポロネーズは、誰もが聴いたことのある曲でしょう。
私は、ショパンの曲では、英雄ポロネーズが一番大好きです。
あと、3番(軍隊)と5番も好きですね。
とにかく、ショパンのポロネーズは優雅で、気持ちが乗るんですよ。
なので、ポロネーズはほんとによく聴きます。
と、まあ、それは置いといて…
ヴィエニャフスキは、第7話でも述べたとおり、ヴァイオリンのショパンとも呼ばれる人物です。
ヴィエニャフスキが作曲した「華麗なるポロネーズ」は、彼の代表曲でもあります。
ヴァイオリン奏者の方にとっては、おなじみの曲みたいですね。
しかも、かなり難しい曲で、スケルツォ・タランテラ並みか、それ以上にもなるそうです。
コンクールなどでも人気のある曲だそうです。
ですが、私は全く知りませんでした😅
ヴィエニャフスキの曲というくらいの知識しかなく、ほとんど聴いたこともありません。
で、実際にYouTubeなどで確認したのですが、アニメで青野くんが弾いていたパートは曲中何度も出てきました。
全体を通して聴くとよく分かりますが、ポロネーズのリズムがふんだんに取り入れられているという印象です。
いや~、知らなかったなぁ。
本当に勉強になりました。
パッヘルベルのカノン
- 曲名:3つのヴァイオリンと通奏低音のためのカノンとジーグ ニ長調
- 作曲者:パッヘルベル
羽鳥先輩が、青野くんと佐伯くんに、オケ部には「奏者のしらべ」という昔から特殊な勉強方法がある…
と、冗談を言った場面で少しだけ流れました。
羽鳥先輩の冗談でしたが、いやいや、なかなかいい勉強法かも。
オケ部だと、実際にあんな感じで勉強している人がいるんじゃないかと思ったくらいです(^^♪
第13話のまとめ・感想
羽鳥先輩がカッコよかったですね。
心に響く言葉が、劇中によく出てきますね。
青野くんも、かなり吹っ切れたようですし。
羽鳥先輩、達観してますね。
やっぱり、あんな感じの性格に憧れます。
あと、裾野先輩、かわいい!
あんなキャラだったのかぁ(笑)
知りませんでした。
そして、小学生の青野くんが、めっちゃ可愛かったですね。
手と足が一緒に出てしまうところとか、お母さんに泣きついてしまうところとか。
うちの息子も小学生なので、親目線で見ちゃいました…
第14話で登場した曲一覧
第14話で登場したクラシック曲です。
「交響曲第9番」第1楽章/ドヴォルザーク
- 曲名:「交響曲第9番(新世界より)」第1楽章
- 作曲者:ドヴォルザーク
鮎川先生のもとで、オーケストラ部が練習していた曲です。
ヴァイオリンだけでなく、他の楽器の奏者も一緒になって合奏練習しましたね。
なかなか音が合いませんでしたが、原田先輩の演奏によって、みんなの呼吸が合うようになりました。
さすが、コンマス!
ヴァイオリンの技術では、青野くんや佐伯くんに劣るかもしれませんが、コンマスとしての力量は圧倒してますね。
とても興味深ったです。
その後、青野くんが山田くんにお願いして、一緒に練習した曲も第1楽章です。
ここでは、いわゆる第1主題が流れていました。
さて、この回でドボ9の第1楽章が登場したので、第12話で取り上げた青野くんの夢の中での演奏は、第1楽章ではないかもしれません。
やはり、第3楽章だったのかも…
間違えている可能性がありますが、第1楽章の解説もご覧くださればと思います。
「交響曲第9番」第3楽章/ドヴォルザーク
- 曲名:「交響曲第9番(新世界より)」第3楽章
- 作曲者:ドヴォルザーク
ハルちゃんと佐伯くんが音合わせをしたときに、練習した曲です。
佐伯くんがちょっとスネているようで、かわいかったです(笑)
第14話のまとめ・感想
町井先輩からヴィオラの話が出てきましたね。
主要なメロディを奏でるヴァイオリンやチェロに対して、ヴィオラはハーモニーやリズムを担当することが多いです。
いわばサポート役に回るため、目立たない存在になりがち。
ですが、ヴィオラがないと、メロディに厚みが出ません。
特にオーケストラでは、ヴァイオリンとチェロの中間の音域を奏でるという特性をいかして、曲全体に奥深さを持たせているという感じです。
ヴィオラが「縁の下の力持ち」と言われる所以ですね。
ちなみに、ドヴォルザーク自身がヴィオラ奏者として活躍していたことがあります。
交響曲第第9番「新世界より」でも、ヴィオラはよく登場します。
また、私の大好きなラフマニノフは、作曲した曲の中でヴィオラにメロディを任せることが多かったようです。
こういうところは、いかにもラフマニノフっぽいですね😆
最も有名であろう「ピアノ協奏曲第2番」でも、ヴィオラは活躍しています。
機会があれば、ぜひお聴きくださればと思います。
第15話で登場した曲一覧
第15話で登場したクラシック曲です。
「交響曲第9番」第2楽章/ドヴォルザーク
- 曲名:「交響曲第9番(新世界より)」第2楽章
- 作曲者:ドヴォルザーク
オケ部の先輩によるトップ練で練習していた曲です。
その後、青野くんが、佐伯くんが演奏していたのを目撃した曲。
さらに、青野くんが、佐伯くんに負けられないと必死に練習していた曲ですね。
どれも素晴らしかったですが、やはり佐伯くんの演奏がもっとも見応えがあったかな。
曲だけでなく、演奏している姿がカッコよかったので、視覚効果もあったように思います。
担当している尾張拓登さんの演奏をたっぷり聴かせていただきました(^^♪
さて、ドヴォルザークの交響曲第9番の第2楽章はとても有名ですね。
後に歌詞がついて、「家路」「遠き山に日は落ちて」などの愛唱歌となりました。
ただ、歌詞をつけたのはドヴォルザーク自身ではなく、お弟子さんです。
何人かの弟子たちによって歌詞付きで編曲されましたが、その中で最も有名なのが「家路」というわけです。
ドボ9の第2楽章は知らなくても、こちらの歌は知っているという方は多いと思います。
原田先輩が語っていたように、小学校の下校の時間に流れることが多いようですね。
私も小学生のときに、学校で流れていたと思います。
ただ、記憶があいまいで定かではありません(汗)
私の場合は、ボーイスカウトをやっていたので、その活動のなかで歌ったのは覚えています。
キャンプファイヤーでは定番の歌でした。
その他、色んな場面でよく歌いましたね。
なので、そちらの記憶の方が強いというわけです。
そして、「遠き山に日は落ちて~」の原曲がドボ9の第2楽章であるのを知ったのは、それより後のことになります。
同じように、ドヴォルザークの原曲を知る前に、「家路」を聴いたり、歌ったりした方は多いのではないでしょうか。
また、アニメの説明にもあったように、第2楽章が「郷愁」をテーマにしているのは間違いないものと思います。
ドヴォルザークが自身の故郷を想って新世界よりを作曲しましたが、とりわけ第2楽章にその想いが色濃く反映されているのが分かりますね。
「カルメン」より「前奏曲(闘牛士)」/ビゼー
- 曲名:「カルメン」より「前奏曲(闘牛士)」
- 作曲者:ビゼー
立花さんが、秋音といつもの3人の女子部員にレッスンした曲です。
しばらくドボ9の演奏が多かったので、久しぶりという感じがしましたね。
そして、何だかんだで、立花さんも可愛いですね😆
第15話のまとめ・感想
救急車のサイレンが😰
前にも述べましたが、青野くんのお母さんには幸せになってほしいと思ってます。
物語の展開からして、そのように思わされてしまいますね。
次回はどうなるんだろ。
このまま、不幸の連鎖が続くというのは嫌だなぁ…
いつものことですが、これからの展開が気になりつつ、放送を待つしかないですね。
第16話で登場した曲一覧
第16話で登場したクラシック曲です。
16話はストーリーに重きをおいた感じで、クラシックは1曲のみとなりました。
相変わらず、BGMが何らかのクラシック曲のように思えて、気になります…
「交響曲第9番」第2楽章/ドヴォルザーク
- 曲名:「交響曲第9番(新世界より)」第1楽章
- 作曲者:ドヴォルザーク
鮎川先生の指揮のもとで、部員たちが演奏した曲です。
第1楽章の出だしの部分が少しだけ流れました。
静寂な雰囲気が、現在の青野くんを取りまく状況を象徴しているような感じがしましたね。
第16話のまとめ・感想
いや~、キツいなぁ…
けど、青野くんが自分の心のうちを、素直に友人たちに打ち明け。
友人たちが親身になって応えてくれるのは、ありがたいですね。
今のところ、それが唯一の救いかなと思います。
次回はどうなるんでしょ。
お母さんが早く元気になって、青野くんがヴァイオリンに打ち込む姿を見たいものです。
第17話で登場した曲一覧
第17話で登場したクラシック曲です。
「くるみ割り人形」より「小序曲」/チャイコフスキー
- 曲名:バレエ組曲「くるみ割り人形」より「小序曲」
- 作曲者:チャイコフスキー
ドイツの小さな町のアマチュアオーケストラが演奏していた曲です。
佐伯くんが自身の生い立ちを語っている中で、ドイツの地図が表示されたときにBGMのように流れ始めました。
その後、アマチュアオーケストラが再び演奏していました。
佐伯くんの8歳のときの姿、かわいかったですね(^^♪
「千里の道も一歩から」という言葉、よく分かります。
「24の奇想曲」第24番/パガニーニ
- 曲名:「24の奇想曲(カプリース)」第24番
- 作曲者:パガニーニ
幼いときの佐伯くんが、青野龍仁のことを知ったとき。
青野龍仁が演奏していた曲です。
アニメでは、青野龍仁の代名詞的な曲になっていますね。
それにしても、ヒラリー・ハーンさんが演奏を担当しているというのが、今だに驚きです。
しかも、パガニーニの24のカプリースだし。
そりゃあ、佐伯くんも感動して、涙流しますわ😆
第17話のまとめ・感想
衝撃の事実が明らかになったわけですが。
しかし、第12話で少し触れたとおり、ウィキペディアで知ってしまったのは、この事実でした。
それだけに、先に事実を知ってしまったのはショックです。
さて、次回は約1か月後の放送となりますね。
17話が、あまりにも苦しくて、やるせない感じで終わったので。
ほんと次回が待ち遠しいです。
ただ、次回予告のセリフでは、少し前向きな様子が見られました。
なので、状況が好転するのを期待しながら、次回まで待つとします。
第18話で登場した曲一覧
約1か月ぶりの放送となりました。
ようやく続きが観れる~と思いましたが。
残念ながら、クラシック曲の演奏はなかったようです。
第18話の感想
でも、BGMがいいですね(^^♪
その時々の情景にとてもマッチしていると思います。
有名なクラシック曲を取り入れているようにも聴こえるのですが、いつものように、この点はちょっと分かりません💦
それにしても、作者の阿久井真さんの心理描写が相変わらずスゴイですね。
でも、青野くんも何とか立ち直ったようで、とりあえず一安心。
次回は感動的なエピソードになりそうで、音楽共々楽しみにしています。
第19話で登場した曲一覧
第19話で登場したクラシック曲をまとめました。
「24の奇想曲」第24番/パガニーニ
- 曲名:「24の奇想曲(カプリース)」第24番
- 作曲者:パガニーニ
佐伯くんの回想シーンで。
小さい時の佐伯くんが青野龍仁のCDを聴いているところから始まって、現在の青野くんと佐伯くんの会話シーンまで流れました。
いつも通り、青野龍仁のテーマ曲という感じですが、今回は佐伯くんの境遇を象徴しているような印象をうけました。
「交響曲第9番」第4楽章/ドヴォルザーク
- 曲名:「交響曲第9番(新世界より)」第4楽章
- 作曲者:ドヴォルザーク
秋音が学校に着いたとき、青野くんと佐伯くんが一緒に演奏していた曲です。
その後、鮎川先生の指揮のもとでオケ部のメンバーが合奏した曲です。
おそらく、ドヴォルザークの交響曲第9番で最も有名な楽章でしょう。
各楽章のテーマが登場し、まさに集大成という感じです。
出だしは力強く始まりそのまま大きく盛り上がりますが、途中で寂しげな旋律が奏でられます。
第2楽章の「家路」のメロディも出てきます。
そして、緩急の対比が繰り返されながら、壮大なクライマックスを迎えます。
これが実に見事で素晴らしい~!
19話では、始めの熱く盛り上がる部分が演奏されていました。
その旋律を、羽鳥先輩の面白い解釈で説明されていましたね。
やはり、ドヴォルザークは鉄道オタクなので(笑)
ここは、まさに「Allegro con fuoco(アレグロ・コン・フォーコ)」
すなわち、「速く、熱烈に」という意味です。
ラストの青野くんと佐伯くんのセリフで持っていかれた感じですが、めっちゃ興奮しました(^^♪
ド迫力の終わり方で、2人のキメ顔がカッコよかったですね。
この続きの演奏は、また別の機会にということになるのかな?
落ち着いた旋律も美しいので、ぜひ聴きたいですね。
また、別の記事でも触れましたが、ドボ9ではシンバルが1回しか登場しません。
一度鳴らすだけなんです。
その登場シーンが、第4楽章の始めの方になります。
上記の音源では2分ちょっとすぎたあたりで、曲調が落ち着くところです。
これは有名なエピソードで、オーケストラあるあるとしてよく知られているお話です。
アニメの演奏の中でシンバルの登場シーンを探すのも、面白いと思います。
あと、よく言われるのは、4楽章の出だしが映画「ジョーズ」のテーマ曲に似ているということ。
言われてみれば、確かに似ているかもしれませんね。
私は、ドボ9の4楽章とジョーズのテーマ曲のどちらを先に知ったのか覚えていませんが、この話を聞くまで全然気づきませんでした。
さらには、ストラヴィンスキーのバレエ音楽「春の祭典」に似ているとも。
最も有名であろう「春のきざし 乙女たちの踊り」の部分ですね。
こちらも言われてみれば、やはり似ているという感じです。
ただ、まあ、ジョーズの音楽を担当した巨匠ジョン・ウィリアムズさんは音楽大学出身ですからね。
ウィリアムズ氏の中でクラシックは土台として築かれているので、ドボ9や春の祭典から意識的にせよ無意識的にせよ、影響を受けたということはあり得ると思います。
特に「春の祭典」はバレエ音楽としては異色の作品。
振り付けはバレエ団によって多少違うと思いますが、曲調とあわせて物凄いインパクトがありますもんね。
なので、個人的にジョーズは春の祭典の影響を受けているのかなという印象を持っています。
第19話のまとめ・感想
感動したなぁ
青春だなぁ
それにしても、青野くんも、佐伯くんも、高校生としてはやたらシッカリしていると感じます。
環境の違いはあれど、私が高校生のときは、あんなに深く考えることはなかったし、問題を解決することもできなかったと思います。
そして、19話後半は、ドボ9の第4楽章。
ついに来たか!という感じです。
「新世界より」 第4楽章
と字幕が出ましたからね。
厳粛な雰囲気でしたが、楽しみでしかない!
機関車が走るという演出も面白かったです。
羽鳥先輩の言葉に共感した方も多いのではないでしょうか。
第20話で登場した曲一覧
第20話で登場したクラシック曲です。
「交響曲第9番」第3楽章/ドヴォルザーク
- 曲名:「交響曲第9番(新世界より)」第3楽章
- 作曲者:ドヴォルザーク
立石先輩が学校でヴァイオリンの音色に気づいたところ、青野くんが教室で練習していた曲です。
今までに何度か登場したドボ9の第3楽章ですね。
ヴァイオリンとチェロのための二重奏曲/コダーイ
- 曲名:ヴァイオリンとチェロのための二重奏曲(第1楽章)
- 作曲者:コダーイ
山田くんの回想シーンで。
佐伯くんと一緒に弾くも、彼の才能に山田くんが衝撃を受けた曲です。
3楽章から成りますが、第1楽章の冒頭のみ少しだけ演奏されました。
「その瞬間、小さなお山の大将は山から転がり落ちたってわけ」という表現が、秀逸でしたね。
ヴァイオリンとチェロのデュオ曲は数多くありますが、その中でコダーイのヴァイオリンとチェロのための二重奏曲は間違いなく最高傑作の1つでしょう。
コダーイは言わずと知れたハンガリーの巨匠。
とりわけチェロ奏者の方にとっては、特別な存在だと思います。
作曲した数は少ないですが、やはり代表作の「無伴奏チェロソナタ」は名曲中の名曲、難曲中の難曲なので。
コダーイの曲の特徴としては、ハンガリーの民俗音楽の要素が取り入れられていること。
ヴァイオリンとチェロのための二重奏曲も、その特徴が存分に生かされています。
また、ヴァイオリンとチェロのどちらもかなりの技術が必要になるみたいです。
無伴奏チェロソナタと同様、それほどではないにしても難曲であるのは間違いないようです。
と、まあ、偉そうに解説しておりますが、私はコダーイの二重奏曲はあまり聴いたことはありません(汗)
それでも名曲であるのは間違いないですし、ヴァイオリンとチェロの迫力あるサウンドには圧倒されますね。
あと、残念ながら、コダーイのヴァイオリンとチェロのための二重奏曲のフリー音源は見つかりませんでした。
2018年に著作権の保護期間が作者の死後50年から70年に延長されましたが、それ以前にすでにコダーイの作品の著作権は消滅しています。
法律の遡及効は認められないのが原則なので、基本的にはコダーイの作品はパブリックドメインになります。
実際、JASRACのデータベースでも、コダーイのヴァイオリンとチェロのための二重奏曲は著作権消滅となっています。
なので、日本国内であれば、特殊な事情がないかぎり自由に使用できるとは思います。
ただ、著作権の問題はややこしくて、私も詳しくはありません。
記事の主旨からそれるので、これ以上深くは掘り下げませんが、コダーイの作品を掲載できる機会があればアップしたいと思います。
第20話のまとめ・感想
前半は立石先輩が主人公、後半は1年生のメンバーたち中心で、2話構成という感じでしたね。
さて、次回のサブタイトルは「ユーモレスク」となっていました。
次回予告の譜面が、いつもの「KANON UND GIGUE」ではなく「Humoreske」となっていたので、アレ?と思いました。
ちなみに7話の次回予告では「Air sul G」とあり、8話でハルちゃんの感動的な「G線上のアリア」の演奏がありました。
とすると、21話では青野くんが「ユーモレスク」を弾くのかな?
おそらく、最も有名な第7曲だと予想します。
ただ、予告の会話を聞くかぎり、子供時代の青野くんとお父さんのセリフだったので、トラウマが蘇ってしまうのではないかとちょっと心配です💦
第21話で登場した曲一覧
21話で登場したクラシック曲です。
ユーモレスク/ドヴォルザーク
- 曲名:ユーモレスク(第7曲)
- 作曲者:ドヴォルザーク
朝早く目覚めた青野くんが昔の楽譜を見つけ、子供のころを思い出しながら演奏した曲です。
青野くんの説明にあったとおり、ドヴォルザークが作曲した全8曲からなるピアノ小品曲集となります。
演奏していたのは、その中で最も有名な第7曲です。
とても有名な曲なので、聞いたことがある方がほとんどでしょう。
曲の特徴などは、青野くん個人の感想を交えて解説されていたとおりですね。
少し付け加えると、ドヴォルザークが病気になったとき、クライスラーがお見舞いにやって来て。
ユーモレスクの楽譜を見つけ、それをヴァイオリン用に編曲したというエピソードがあります。
このエピソードが本当なのかどうかは分かりませんが、クライスラーが編曲したヴァイオリン版が大きな人気になったのは事実ですね。
またユーモレスクというタイトルは、英語のユーモアと同じ語源のフランス語ですが、特に深い意味はないそうです。
あえて日本語に訳せば、いわゆる「奇想曲」、あるいは「気まぐれな楽曲」というところです。
ドヴォルザーク自身も気まぐれなノリで作曲したのかもしれません。
第7曲が独立して演奏されることがほとんどなので、ユーモレスク全8曲を聴く機会はあまりないと思います。
ですが、全て通して聴くと、いかにも奇想曲という感じがします。
最も有名な第7曲でも、アニメで「曲の中盤 おだやかな時間は一変する」とあるように、途中で急に哀愁をおびた曲調になりますよね。
上記の音源だと、1分20秒すぎたあたりです。
ここに差しかかると、なぜ急に悲しくなるの?といつも思います。
なので、決して明るい曲ではないという印象です。
むしろ、人生山あり谷ありを表現しているのかなと思うことがあります。
でも、最後はまた穏やかな曲調に戻るので、「大丈夫 雨はやむから」と思いたいですね。
「交響曲第9番」第3楽章/ドヴォルザーク
- 曲名:「交響曲第9番(新世界より)」第3楽章
- 作曲者:ドヴォルザーク
定期演奏会のオーディションの曲。
再テストということで、鮎川先生の前で青野くんが弾いた曲ですね。
もの凄い迫力でした。
素晴らしい演奏でしたね(^^♪
第21話のまとめ・感想
ユーモレスク、ガチで感動しました😭
朝顔のくだりは、ほんと切なかったですが。
でも、エンディングの後に微笑ましい一コマでうまく締めてくれました。
ほっこりするエピソードでしたね(^^♪
ただ、ちょっと気になることが…
青野くんのお母さんの名前が出てこない!?
クレジットを見ても「青野の母」となっていて、名前がありません(汗)
青野パパは龍二という立派な名前があるのに。
青野ママの名前が知りたいです…
第22話で登場した曲一覧
22話で登場したクラシック曲です。
「アルルの女」第2組曲 メヌエット/ビゼー
- 曲名:「アルルの女」 第2組曲 第3曲「メヌエット」
- 作曲者:ビゼー
海幕高校オーケストラ部の定期演奏会の会場で、ロビーコンサートで演奏されていた曲。
だと思うのですが…
ほんの少しだけ流れたので、ちょっと自信がありません(汗)
アルルの女は、ビゼーが手がけた有名な組曲ですね。
カルメンと並んでビゼーの二大傑作と言ってよいでしょう。
なかでも第2組曲のメヌエットはとても有名です。
フルートとハープが奏でる美しい音色は、至るところで聴く機会が多いと思います。
たまたまですが、電話の保留音に使われているのを聴いたことがあります。
ただし、このメヌエットはもともとはビゼーの歌劇「美しきパースの娘」の曲でした。
それをビゼーの友人の作曲家ギローが編曲し、アルルの女に取り入れたものです。
私はこの辺の詳しい事情は知りませんでした。
どこかで聞きかじって、そういう事情があったのねという程度の認識でした。
ところで。
アルルの女は、とんでもなくカオスな物語です。
衝撃のラストは戦慄そのもの。
個人的には、カルメンの比ではないという印象です。
第2組曲の最後の曲はファランドールで、こちらも有名な曲です。
メヌエットより有名かもしれません。
そして、ファランドールの中で、この物語を象徴する悲劇を迎えるわけです。
第2組曲ではメヌエットはファランドールの前に演奏されます。
一時期、アルルの女のCDを何度も聴いたことがあるので、メヌエット→ファランドールという曲順が頭から離れません。
そのため、メヌエットは悲劇を前にした束の間の美しいひと時という印象があります。
嵐の前の静けさ…
やはり、アルルの女という作品のストーリーを中途半端に知ってしまったからでしょう。
ほんと個人的な感想でしかないのですが、アルルの女のメヌエットを聴くと、穏やかな安らぎの中でもちょっとした不安を感じることがあります(汗)
美しく青きドナウ/ヨハン・シュトラウス2世
- 曲名:美しく青きドナウ
- 作曲者:ヨハン・シュトラウス2世
武田先生が高校生時代にオケ部で練習していた曲です。
譜面には「An der schönen Blauen Donau」とあり、これは「美しく青きドナウ」のことです。
ですが、演奏はされていないと思います。
BGMがそうなのかなとも思いましたが、違うような…
高校生時代の鮎川先生がトランペットを吹いていましたが、美しく青きドナウの練習をしていたのかもと勝手な想像をしております💦
あくまで参考程度にとどめておいてくださいませ。
美しく青きドナウは、ヨハン・シュトラウス2世の代表曲ですね。
シュトラウス2世はたくさんのワルツを作曲していますが、美しく青きドナウはその中で最も有名なものの1つです。
オーストリアでは、今でも「第二の国歌」と呼ばれるほど国民に愛される曲となっています。
タイトルにもある「ドナウ」とは、ヨーロッパを流れる大河のこと。
そのドナウ川の流れを音楽で表現しています。
美しく青きドナウの楽曲の構成を簡潔に説明すると
- 序奏:川のせせらぎで始まるような、ゆっくりとした部分
- 第1ワルツ:本格的なワルツの始まり。明るい旋律
- 第2ワルツ:軽快なリズムから、途中でゆったりした感じに
- 第3ワルツ:終始軽やかで舞踏的な雰囲気
- 第4ワルツ:最も優雅で軽快な旋律
- 第5ワルツ:徐々に雄大になっていき、そのままクライマックへ
- コーダ(終結部):全ての旋律が集まった後、第1ワルツの旋律に戻り、テンポが速くなって締めくくられる
となるそうです。
じっくりと聴くと、軽快なリズムとゆったりとした美しい旋律が見事に融合されているのが分かりますね。
さて、ここからまたクラシックの小ネタになります。
An der schönen Blauen Donauはドイツ語で、日本語に翻訳したものが「美しく青きドナウ」となります。
ここでのschönenが「美しい」という意味になります。
一方で「美しき青きドナウ」と表記されることもあります。
自然な日本語では「美しき青きドナウ」の方がふわしいような気がします。
私も初めて知ったときからしばらくは、「美しき青きドナウ」だと思っていました。
ですが、最近は「美しく青きドナウ」という日本語タイトルの方が優勢で、定着してきている感じです。
もちろんどちらも間違いではないと思いますが、「美しく青きドナウ」が一般的と認識しておいた方がよさそうです。
第22話のまとめ・感想
22話も感動する回でしたね。
武田先生のお話も、原田先輩の贈る言葉も、泣けるわ~😭
私の場合は高校生のときはそうでもなかったですが、大学生のときにバリバリの体育会系の部活をやっていたので、よく分かります。
引退式などで先輩から言葉を贈られるんですよね。
逆に私が引退するときは、後輩に言葉を贈ると…
あと、原田先輩が気を取り直して再び演説をしたとき、呪術廻戦の虎杖くんが出てきた気がしました(笑)
同じ声優さんだよという話をしたら、うちの息子がえらい感心してました。
榎木淳弥さんの声って、ほんと凛々しいですね(^^♪
さて、次回は定期演奏会のようですが、予告の譜面が「CARMEN Prelude」となっていました。
ということは、定期演奏会でカルメンの前奏曲も演奏されるのかもしれません。
今まで演習してきた曲がたくさん登場しそうで、楽しみですね☺
第23話で登場した曲一覧
23話で登場したクラシック曲です。
オープニングの「Cantabile」とエンディングの「夕さりのカノン feat.『ユイカ』」は流れませんでした。
でも、とても素敵な演出でしたね。
「カルメン」より「前奏曲(闘牛士)」/ビゼー
- 曲名:「カルメン」より「前奏曲(闘牛士)」
- 作曲者:ビゼー
海幕高等学校シンフォニックオーケストラ部定期演奏会の第1曲目。
秋音が演奏しながら、心の中で解説をはさんで語っていた曲ですね。
前奏曲とあったので、カルメン第1組曲の前奏曲そのまんまかと思ってましたが、Les Toreadorsでした。
やはり、一般的にはLes Toreadors(闘牛士)が前奏曲と呼ばれることが多いみたいです。
「くるみ割り人形」より「小序曲」/チャイコフスキー
- 曲名:バレエ組曲「くるみ割り人形」より「小序曲」
- 作曲者:チャイコフスキー
定期演奏会の第2曲目です。
ハルちゃんの回想シーンとともに、くるみ割り人形の解説も触れられました。
幼い時のハルちゃんがとても可愛かったですね(^^♪
「くるみ割り人形」より「花のワルツ」/チャイコフスキー
- 曲名:バレエ組曲「くるみ割り人形」より「花のワルツ」
- 作曲者:チャイコフスキー
定期演奏会の第3曲目です。
こちらもハルちゃんの回想シーンとともに演奏されました。
花のワルツは、くるみ割り人形で最も有名でかつ優雅な曲ですね。
ドラマや映画、CMなどでもよく使用されています。
バレエの第2幕で演奏されますが、物語としては主人公のクララがお菓子の国を訪れるという場面です。
このシーンでは、24名のバレリーナがお菓子の精として踊るのが一般的です。
またバレエ組曲では最後の曲として登場し、クライマックスを迎える盛り上がりを演出します。
そして、バレエの舞台ではラストの演出が2通りあったりします。
一応原作童話に基づいたラストですが、どちらも素敵な終わり方だと思います。
ここではネタバレしないようにオチは明かしませんが、ぜひバレエのくるみ割り人形もご覧くださればと思います。
さて、アニメでは花のワルツがとても美しい旋律で奏でられ、魅了されてしまいますね。
私は、くるみ割り人形では小序曲とロシアの踊りが好きですが、アニメの花のワルツには圧倒されました。
クラシックにはたくさんのワルツがありますが、やはり花のワルツは特に素晴らしい一曲ですね。
「四季」より「春」第1楽章/ヴィヴァルディ
- 曲名:「四季」より「春」第1楽章
- 作曲者:アントニオ・ヴィヴァルディ
定期演奏会の第4曲目です。
3年生がメインとなり、原田先輩がソロとして指揮をとりながら演奏した曲ですね。
高橋先輩の回想シーンを交えながらの演出でした。
「四季」より「夏」第3楽章/ヴィヴァルディ
- 曲名:「四季」より「夏」第3楽章
- 作曲者:ヴィヴァルディ
定期演奏会の第5曲目です。
こちらも高橋先輩が回想シーンを振り返り、心の中で語りながら演奏していましたね。
ヴィヴァルディの四季の春の解説でも述べたとおり、夏は3楽章ともどんよりした雰囲気です…
日本での陽気なイメージとは全然違います。
もちろん日本でも、夏のイメージは一部厳しいものがあるとは思いますが。
それでもヴィヴァルディの四季の夏は聴いていると、心が落ち着きません。
これはお国柄と時代が日本の夏のとらえ方と違うので、夏の印象も異なるからでしょう。
例えば夏の第2楽章のソネットには、無数のハエが群れをなすというものもあります。
そのため羊飼いは疲れて休まることがないと…
これなんかは、さすがに現在の日本では一般的には見られない風景ですね💦
とにかく四季の夏は全楽章通して、ひたすらその災いを表現している曲と言えると思います。
そしてアニメでも演奏された第3楽章は、高橋先輩が語っていたようにイタリアの過酷な夏の嵐を表現しています。
夏の楽章の中では最も激しい曲。
というか、四季の全楽章通じて最も激しい曲でしょう。
そのため、四季の中では特にドラマティック部分でもあります。
アニメでは、聴いていた小さな子供が「こわい~」と言っていましたが、やはり初めて聴くと不気味に感じると思います。
夏の第3楽章のソネットは
空は雷鳴をとどろかせ
稲妻が走り
あられが降り
熟した穀物の穂を痛めつける
となります。
荒れ狂う自然現象にあらがえず、報われない様子が感じられますね。
楽曲でも弦楽器が素早く弾かれたり、音に強弱をつけたりしながら、この様子を表現しているというわけです。
第23話のまとめ・感想
ここ数回連続で感動する話が続きましたが。
23話は鳥肌ものでした。
オープニングとエンディング曲は流されず、全編クラシック曲の演奏で定期演奏会そのものを鑑賞しているような感じでした。
しかも各キャラクターごとにテーマとなる曲が設定され、それぞれの想いをのせながら流れるという演出が素晴らしい!
神がかってましたね😆
部分部分では、他の回の方が心を動かされるシーンはありましたが。
1話全体を通してみると、23話はまさに神回だったと思います。
さて次回は最終回となるようです。
サブタイトルは「新世界より」
次回予告のおなじみの楽譜は「交響曲第9番」
いつものセリフはありませんでしたが、ドボ9が演奏されるのは間違いないでしょう。
さすがに全楽章を流すには時間が足りないので、ダイジェスト版になると思います。
それでも今までの練習の集大成として、素晴らしい演奏が聴けるものと期待しています(^^♪
第24話(最終話)で登場した曲一覧
24話、最終回で登場したクラシック曲です。
オープニングテーマは流れましたが、エンディングの「夕さりのカノン feat.『ユイカ』」は流れませんでした。
交響曲第9番/ドヴォルザーク
- 曲名:交響曲第9番(新世界より)
- 作曲者:ドヴォルザーク
海幕高校オーケストラ部定期演奏会の最後の曲。
ドヴォルザークの交響曲第9番第1楽章~4楽章まで全楽章通して演奏されました。
オープニングテーマ/「Cantabile」
- 曲名:「Cantabile」
- 作詞:竹中雄大
- 作曲:竹中雄大/沖聡次郎
アニメのラストを締めくくる曲という感じで、オープニングテーマが流れましたね(^^♪
第24話のまとめ・感想
最終回、やっぱり感動しましたね😂
定期演奏会の後、ほとんど皆泣いてましたもんね。
あんなの見せられたら、もらい泣きしますわ。
そして、ドヴォルザークの新世界よりが何より素晴らしかったですね。
部員たちそれぞれの想いを乗せながら、1話まるごと使って全楽章演奏されました。
新世界よりは実際には40分くらいあるので、アニメでは半分ほどの長さのダイジェスト版が流れたという感じでしょうか。
素晴らしい演出だったと思います。
そしてラストシーンで、思いっきりノスタルジックな気分に陥りました。
あ~、終わっちゃった~
と、余韻に浸るのも束の間で!
アニメ「青のオーケストラ」
第2期制作決定!
よかった、よかった~
いつ放送なのかは分かりませんが、楽しみですね(^^♪
アニメを見て原作のコミックを読もうと思っていましたが、第2期まで待とうかと考えています😅
第2期でもどんな曲が登場するのか、楽しみは尽きません。
このブログでまた曲紹介をするかもしれませんが、そのときはまたよろしくお願いいたします。
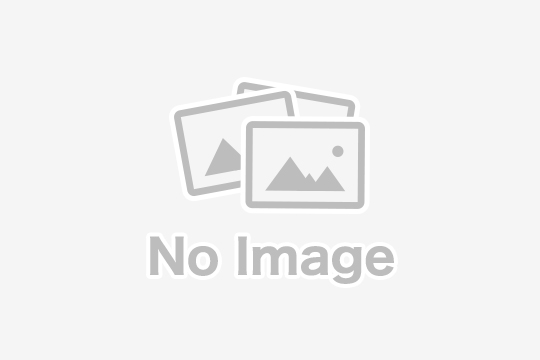
青野龍二が演奏していた曲がとても知りたかったので有り難いです!
A.O様
参考になったようで、こちらこそありがたいです!
コメントありがとうございました。